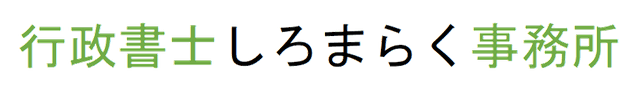みなし登録電気工事業者開始届出
電気工事業をする事業者が建設業許可をとったり、建設業許可をもってる場合は、このみなし登録届出をすることになります。
建設業許可は500万以上の工事を請けるためにとるものなので、建設業許可をとってなくても500万未満の電気工事をするのは建設業法的にはオッケー。
ですが、電気工事業法で電気工事業者登録をしないと電気工事業はできないとなっているので、電気工事業の登録は必要というわけです。
また、建設業許可の業種は電気工事に限らず全ての業種が対象なので、とび土工工事や鉄筋工事で建設業許可をとったり、とってたりしても、電気工事業をする場合はみなし登録届出をすることになります。
要件とか提出書類は登録電気工事業者登録申請とほぼ変わらないので、そちらで確認してください。
みなし登録届出は手数料はありません。
先に電気工事業者登録してるのにみなし登録しないといけんの?
あ・・・ありのまま電気工事業法に書いてある事を話すぜ!
e-Gov法令検索
(建設業者に関する特例)
第34条6項
登録電気工事業者が建設業法第2条第3項に規定する建設業者となったときは、その者に係る第3条第1項又は第3項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
「登録電気工事業者が建設業許可をとったら、電気工事業者登録は効力を失う」
な、何を言ってるか分からねーとは思うが(略
ということで自動的に登録抹消みたいになります。
でも、みなし登録届出をすれば建設業許可受けたときとかにさかのぼって登録電気工事業者とみなす「みなし登録電気工事業者」の扱いになるということです。
な、何を言ってるか分からねーとは思うが(略
正直、それ行政側でやっといてくれん?と思う。
主任電気工事士と専任技術者の要件の違いに注意
電気工事業者登録(みなし登録も)と建設業許可には、それぞれ営業所に主任電気工事士と専任技術者を置かないといけないという要件があります。
登録電気工事業者の主任電気工事士は第一種電気工事士と第二種電気工事士に限られてますが、建設業許可の電気工事の専任技術者は他に電気工事施工管理技士などの資格でもなれることになっています。
つまり、電気工事で建設業許可をとれても、第一種・第二種電気工事士がいなければ、みなし登録電気工事業者にはなれないということです。
電気工事士以外の方を専任技術者にして建設業許可をとったあとに電気工事業を始めるということでみなし登録届出の手続をする事業者は注意してください。
兼務可能ですが要件が違うので、主任電気工事士と専任技術者が違う人ということもありえますね。
廃止届出
登録電気工事業者が建設業許可を受けたら自動で登録抹消みたいになるのに、事業者が電気工事業廃止届出書を出さないといけません。
な、何を言ってるか分からねーとは思うが(略
なので、みなし登録届出をしても廃止届出が出されていないと、みなし登録電気工事業者届出受理証が発行されないので注意しましょう。
通常はみなし登録届出と廃止届出を同時に出すことになります。
先に建設業許可を受けた事業者が電気工事業をはじめる場合は、廃止届出はいらず、みなし登録届出だけで大丈夫です。
更新はないけどある
みなし登録も有効期限がありますが、みなし登録電気工事業者は登録電気工事業者じゃないので更新という手続はありません。
ですが、建設業許可で5年毎の更新があり、建設業許可更新をしたら建設業許可番号が変わるから、みなし登録の手続をした際の建設業許可番号の変更について変更届出をします。
すると、みなし登録の有効期間が更新した建設業許可の有効期間と同じ期間に変更(5年延長)されるので、それが実質更新の手続になります。
もし建設業許可の更新をせずに有効期間が切れたり、建設業許可がなくなったら、みなし登録の効力も切れて電気工事業ができません。
建設業許可がなくなったあとに電気工事業をするためには、もっかい建設業許可をとってみなし登録届出を出すか、建設業許可をとらないのであれば新規で登録電気工事業者登録申請をすることになります。
建設業許可の有効期限はしっかり把握しておきましょう。更新期限の通知とかはないです。
手続や効力は建設業許可とも連動することがあると認識してください。
手続の流れ
①面談
お話をうかがって手続の内容などについて説明のため営業所などの確認も兼ねて営業所に伺います。
②見積提示
面談の内容にもとづいて見積書を提示します。
報酬の着手金を頂いてから書類作成に進みます。
③書類作成
珍しい状況でなければ依頼者側でのめんどうな作業はありません。
④書類提出
⑤登録証交付
登録証が郵送されてきます。
残りの報酬と諸費用などを頂きます。